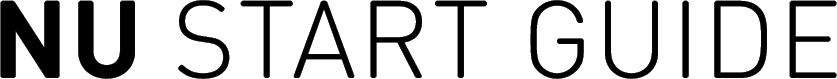2025.05.14
- 大学生活全般
期末レポート・試験の「布石」を5月から打っておこう
こんにちは、名古屋大学大学院創薬科学研究科修士1年の小林です。新生活のドタバタもようやく落ち着いてきた5月。キャンパスの雰囲気にも慣れ、友達や授業のリズムも少しずつ掴めてきたという方も多いのではないでしょうか。でも、そんな「ひと段落」の今こそ、実は期末レポートや試験に向けた“準備期間”のベストタイミングなんです。私自身、1年生のときは「今はまだ早いかな」と思ってのんびりしていたら、7月に突入してレポートやテストが一気に押し寄せてきて、深夜の課題ラッシュに追われて毎日徹夜という経験をしました。そんな経験を踏まえて、今回は「5月のうちに仕込んでおくと未来が助かること」をご紹介します。
5月は「静かな助走期間」
GWが明けた頃から部活やサークルの新歓も落ち着き、大学全体の空気もどこかまったりしてきますよね。この“まったり感”に油断してしまうと、6月中旬以降、気づいたときには課題・課題・課題……という地獄のスケジュールになっていることも。だからこそ、この5月は「今は何もないけど、未来のために一歩先回りする期間」として活用できると、本当に強いです。
シラバスを“もう一度”ちゃんと読む
履修登録のときにパッと見て終わりになっていませんか? 実は5月のこのタイミングでもう一度じっくり読み直すと、今後の大学生活がぐっと楽になります。多くの授業では評価方法や提出物の内容、スケジュールの全体像がシラバスにすでに書かれています。たとえば、「レポート提出が評価の70%を占める」、「プレゼンとレポートの両方が必要」、「最終週に小テストがある」など、授業によって求められる成果は本当にバラバラです。
今のうちにそういった情報を整理しておけば、どの授業にどれだけエネルギーを注ぐべきか、優先順位がはっきりしてきます。なんとなく課題に追われるのではなく、「これは今やっておくと楽になる」と見通しを持って行動できるようになります。おすすめは、シラバスの要点をスプレッドシートやノートにまとめておくこと。評価割合・提出物・重要な日付・先生のコメントなどを一覧にしておくだけで、期末の計画がぐっと立てやすくなります。
それに、先生がシラバスで強調していること(例えば「議論への参加を重視します」、「フィードバックは積極的に利用してください」など)を把握しておけば、授業内外での振る舞いも工夫できて、成績アップにもつながります。少し面倒に感じるかもしれませんが、未来の自分を助ける“情報の地図”をつくるつもりで、今一度シラバスを開いてみませんか?
期末に出そうなテーマを予想してみる
 今やっている授業の中に、「これ、期末でレポートに出されそうだな」、「この概念、たぶん試験で問われるぞ」という直感、ありませんか? その“なんとなく気になる”という感覚が、期末対策の最初のヒントになります。私は授業中に先生が何度も繰り返していたキーワードや、スライド・配布資料で太字や赤字になっていた部分を、意識的にメモするようにしています。おかげで期末前に「どこを復習すべきか分からない」と焦る時間がグッと減りました。
今やっている授業の中に、「これ、期末でレポートに出されそうだな」、「この概念、たぶん試験で問われるぞ」という直感、ありませんか? その“なんとなく気になる”という感覚が、期末対策の最初のヒントになります。私は授業中に先生が何度も繰り返していたキーワードや、スライド・配布資料で太字や赤字になっていた部分を、意識的にメモするようにしています。おかげで期末前に「どこを復習すべきか分からない」と焦る時間がグッと減りました。
特に社会系、倫理系などの授業では、「この講義の目的は?」、「どういう視点で物事を考えるべきか?」といった問いがレポートのテーマになりやすいですし、理系の講義では「理論の応用」、「定義の違い」、「プロセスの説明」といったポイントが試験に出やすい傾向があります。先生が「これは重要なので覚えておいてください」と言ったときや、話し方に熱がこもっていたときは、試験問題の“伏線”であることも少なくありません。
授業のスライドに簡単なメモを添える、1週間ごとに「これは出そう」と思った項目をリストにしておくなどを今のうちから始めておけば、期末直前にゼロから準備を始める必要がなくなります。むしろ「これは予想していた通りだ」と安心感が生まれ、自信を持って取り組めるようになるはずです。
情報は、集めておくだけで“武器”になります。授業中の直感や印象に、ぜひ意識を向けてみてください。
課題は“提出日ではなく、着手日”で管理する
私が学部時代に大きく生活を変えるきっかけになった習慣が、「課題管理の仕方」でした。以前は「6月10日が提出期限」とだけ把握して、結局いつも締切ギリギリに焦って取り組んでいました。でも、「この日に着手する」と“開始日”を設定するようにしてから、気持ちにも時間にも余裕が生まれました。
たとえば、「5月25日に構成」、「5月28日に文献探し」、「6月3日に下書き」、「6月7日に見直して提出」といったように、いくつかの小さなステップに分けて、それぞれに着手日を設けます。こうすると、「提出日までにやらなきゃ」という漠然とした不安ではなく、「今日は構成だけやればいい」と明確な目標で動けるので、集中しやすく精神的にも楽になります。
スケジュール帳やカレンダー、ToDoリストアプリ(たとえばGoogleカレンダーやNotion、TickTickなど)を活用すれば、こうしたステップを視覚的に管理することもできます。特にカレンダーに「〇日に構成、〇日に下書き」など予定を書き込んでおくと、自分の中で“課題が進んでいる感覚”が得られて、モチベーションの維持にもつながります。自分のペースで一歩ずつ進める仕組み、ぜひ試してみてください。
ノートや資料は“後の自分”へのプレゼント
期末直前に「これ誰が書いたの…?(自分だけど)」となるノート、よくありますよね。私はこれを防ぐために、「未来の自分にメッセージを書く」感覚でノートを取るようにしています。授業の最後に一言「今日の内容=〇〇が大事」とメモし、難しい部分には「この辺、テストに出そう!後でもう一度見る」と書き込みます。見返したときに自分が“使いやすい”形になっていると、直前の復習が何倍も効率よくなります。
「1日15分だけやる」を自分に課してみる
「毎日2時間復習しよう!」は続きませんが、「15分だけやる」はなぜか続けられるんですよね。授業のスライドを軽く見直す、ノートを整理する、用語をノートに書いてみる。そういう小さな行動の積み重ねが、結果的に大きな力になります。やる気がある日は30分やってもいいし、気分が乗らない日は本当に15分で終了してもOK。「完璧じゃなくていい」を自分に許してあげることが、長く続けるコツです。
試験・レポート情報を友達と共有しておく
「この授業って試験だったっけ?レポートだったっけ?」。情報共有は期末対策の第一歩です。友達に「○○先生、去年も同じテーマだったらしいよ」と聞いていたおかげで、余裕を持って提出できたことが何度もあります。「自分だけが情報を握っておこう」と思わずに、お互い助け合うスタンスでいれば、期末の不安も軽減できます。
小さな“ご褒美”も忘れずに
私は「課題を1時間やったら好きなお菓子を食べる」、「ノートを整理した日はお気に入りのカフェに行く」など、自分なりのご褒美ルールを作っていました。小さなことでも、自分の努力を認めてあげることは、モチベーション維持にすごく効きます。
5月だからこそ作れる“自分だけの学びの型”
ここまで紹介してきたことを実践するには、もちろん時間も気力も必要です。でも、5月は「日常にまだ余白がある」月。たとえば、「自分は朝型だから午前に復習を回そう」、「水曜の空きコマは課題をやる時間にしよう」など、自分の学び方を試行錯誤してみましょう。私自身、空きコマで30分だけ次の授業の復習をしておくだけで、レポートに必要な情報が自然と頭に入ってくるようになりました。こうした小さな工夫で6月以降の忙しさにも柔軟に対応できるようになります。
おわりに
5月は少しだけ前に進んでおくのにちょうどいい時期です。まだレポートも試験も遠く感じる今だからこそ、焦らず止まらず、小さな行動を積み重ねていきましょう。すべての課題を完璧に終わらせる必要も、すべての授業を完璧に理解する必要もありません。“今日やったことが、1ヶ月後の自分を助ける”。そんな意識で日々を過ごしていけば、期末の自分が「あのときやっておいてよかった」と笑っているはずです。大切な助走期間を丁寧に過ごしてみてくださいね。拙い文章ではございますが、最後までお読みいただき、ありがとうございました。
Profile
所属:創薬科学研究科博士前期課程1年生
出身地:愛知県
出身校:愛知県立岡崎高等学校