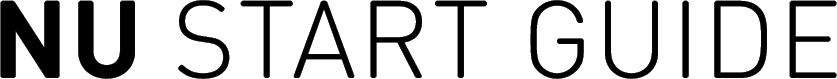2024.10.22
- 大学生活全般
化学生命工学科はどんなところ?
みなさん、こんにちは!名古屋大学工学部化学生命工学科3年の小林です。今回は私が所属している化学生命工学科について紹介したいと思います。名古屋大学を受験しようか悩んでいる人や、化学生命工学科に興味がある人はぜひ一読してほしいです。名古屋大学には、工学部の化学生命工学科と理学部の化学科という化学に関する似ている学科がありますので、その二つの違いや特徴などにも触れながら解説していきたいと思います。私が通っている学科の魅力をお伝えできればと思いますので、ぜひ最後まで読んでください!!
化学生命工学科の概要
名古屋大学の化学生命工学科は、その名前にもある通り、化学と生物学の両方について学べる学科です。化学と生物の融合として、バイオテクノロジーや環境問題、医療など、幅広い分野に対応できる技術と知識を学ぶことができます。ただ体感として、生物学よりも化学の方が比重は重いと思います。
「生命化学」という授業では、生体内でどのように化学が関連しているのかについて学びます。また、微生物と化学の関連性については「生物反応工学」でも学ぶことができ、今ホットな分野である遺伝子改造技術や、微生物を用いた油脂の分解などについて受講できます。他にも、ガッツリ高校の化学の延長として「有機化学」、「無機化学」についても非常に詳細に学びます。「有機化学」は反応機構と呼ばれる、どのような原理で、どのような電子の流れで化学反応が起こるのかということも学習するため、化学反応が起こるメカニズムに興味がある人はとても楽しいと思います。
このように、化学生命工学科には化学に関する分野の授業がたくさんあります。また、研究室に配属後(4年生以降)は、最先端の技術や機器を用いて実験ができるので、実践的なスキルを身につけることもできます。
理学部の化学科との違い
名古屋大学理学部に化学科もありますが、工学部の化学生命工学科との大きな違いは、化学に対するアプローチの仕方だと思います。理学部の友達の話を聞く限り、理学部化学科は主に化学の基礎理論や実験に重点を置いています。一方、工学部化学生命工学科は、化学の知識を応用して、新しい技術を創出する(ある意味工学的な)実験をしたり、生体内のペプチドについて化学的に理解を進めたりという、化学を利用して生物学を発展させるような研究をしています。このため、非常に簡潔な言い方をしてしまえば、理学部は基礎研究を重視しており、工学部は今ある技術や新しい技術を応用、活用して形あるものに変える、より発展的な内容にチャレンジしていると捉えられます。そのため、工学部では実践的な視点から学ぶことが出来ると思います。
また、カリキュラムの都合上、専門的な内容を学ぶスピードにおいても、化学科と化学生命工学科には違いがあります。名大の理学部には「学科分属」という制度があることをご存知でしょうか。理学部に入学した場合、1年次には学科に属さず、全学共通教育を受けます。ここでは数学や理科の基礎科目だけでなく、物事に対する考え方や議論の方法について学ぶリテラシー、人文社会系の教養科目、外国語、そして分属先にまつわる科目の基礎を身につけます。その後、1年終了時に、希望や成績などによって各学科への配属が決定され、数理学科、物理学科、化学科、生命理学科、地球惑星科学科の5学科に分かれます。そのため、化学科で専門的なカリキュラムが始まるのは、実質2年生からになります。
一方で、工学部には分属はなく、合格したら化学生命工学科に配属され、1年生からすぐに発展的な化学を学びます。前述した有機化学の授業も1年生から学び始めます。より重点的に化学こそを学びたい!と思っている化学好きな人には、化学生命工学科がより適しているのかもしれません。ただ、理学部のように、1年次に化学以外の科目に触れられるのも魅力ではあるため、自分の興味に応じて選ぶのが良いと思います。
化学生命工学科の魅力
 実際に化学生命工学科に所属している立場から、魅力についてお伝えしたいと思います。まずやはりなんといってもバイオと化学を両方学べることが魅力だと思います。私は化学だけでなく、遺伝子工学や生物学などにも興味があったため、この化学生命工学科で学べる内容はどれも非常に面白く興味深かったです。生物学やバイオテクノロジーにも興味がある方にとって、この学科は非常に魅力的だと思います。
実際に化学生命工学科に所属している立場から、魅力についてお伝えしたいと思います。まずやはりなんといってもバイオと化学を両方学べることが魅力だと思います。私は化学だけでなく、遺伝子工学や生物学などにも興味があったため、この化学生命工学科で学べる内容はどれも非常に面白く興味深かったです。生物学やバイオテクノロジーにも興味がある方にとって、この学科は非常に魅力的だと思います。
また、対象とする学問領域が広い、つまりさまざまな分野について研究できることも魅力だと思います。化学生命工学科は、物質の構造、性質、反応を理解するための学問である化学を「基盤」として学び、生命体まで関連する幅広い物質、現象、機能を研究対象とする学科です。新しい材料や医薬品の創成につながる新規反応、新規物質の開発から、生命現象の分子レベルでの解明、生物の工学的応用に至るまで、現代社会を支える上で益々重要となっていく多種多様な分野について、最先端の研究をしている先生の元で救育を受けることができます。今の時代を担う化学の最先端を実際に見られるのはとても魅力的です。私も実際にいくつかの研究室に見学に行きましたが、どの研究室も非常に興味深く、どれを研究しても良いと言えるほど面白かったです。まだ進路に悩んでいる高校1、2年生は、夏のオープンキャンパスにぜひ来てみてください。化学生命工学科も研究紹介をしているので、どのような研究をしているのか覗いてみるとかなりイメージがつくと思います。
カリキュラムの流れ
実際のカリキュラムについて1年次から順を追って説明していきたいと思います。
まず、1、2年次には、専門的でありながら化学の基礎となる物理化学、有機化学、無機化学、分析化学、生命科学などを体系的に学ぶことで基礎力を養います。授業でのインプットだけではなく、演習や実験で学んだことをアウトプットさせ、実践力を向上させます。高校の授業では、先生が教科書の内容を説明して、課題でその演習をすることが多いと思います。しかし、大学での学びはかなり高度で難しい内容が多いので、自分一人で演習をすると分からない箇所が多く出てきます。そのため、このカリキュラムのように、まず座学で学び、演習までセットで学習するという形式は、非常に学生のためになると感じています。
続く3年次には、生命工学、高分子化学、材料化学、生物情報工学などの講義と演習で工学的な視点を養い、1、2年次とは対照的に応用力を鍛えます。また、授業形式だけではなく、本格的な学生実験も始まります。週の半分以上、午後に4時間ほどかけて化学的な実験を行います。この学生実験では自分でフローチャートを書き、実験の目的や操作を理解してから実験します。非常に応用的で難しい部分も多いですが、今まで培ってきた知識を基に実験が進むので、それだけ達成感や面白さがあります。また、実験をして終わりではなく、実験の後には必ずレポートを書きます。このレポートがとても重要で、実験の目的や操作、結果と、そこから考えられる考察まできちんと書かなければいけません。書くのには時間がかかりますが、しっかりと科学的な考察をすることは4年次以降の研究にも役に立つので、重要な課題だと考えています。
最終学年である4年次には各研究室に配属されます。化学生命工学科には、生命分子工学専攻、応用物質化学専攻、有機・高分子化学専攻の大きく分けて三つの専攻があり、各専攻に分かれた後、より細分化された研究室へと分かれていきます。4年次での研究でその専門分野の基本を習得するとともに、卒業研究として最先端の研究を行うことになります。
以上のカリキュラムを通して、 化学に基づく基礎力、応用力を身につけることができます。4年生についてはまだ経験していないため分かりませんが、3年生までのカリキュラムは非常にためになるものであり、1年生から段階的に専門的な化学について触れることが出来るので、しっかりと授業を受けていれば、高度な内容も理解できるように設定されていると思います。
化学生命工学科の学習環境
どんな環境で、どのような雰囲気で授業が行われているのか、気になる人も少なくないと思います。まず授業の種類として、1年次に多い一般教養科目と2年次以降に多い専門科目の二つがあります。一般教養のときは全学教育棟という建物で、他学部他学科の人とも一緒に授業を受けることが多いです。他学部の人と交流できる機会は高学年になるほど少なくなるので、このときに仲良くなっておくと交友の幅が広がると思います。全学教育棟には高校と同じ30人程度収容の小さな教室と、100人ほど入る大きな教室がありますが、ほとんどを小さな教室で受けた記憶があります。
化学生命工学科の専門科目は、工学部1号館という建物で受講します。専門科目はほとんど学科のメンバー全員(100人ほど)で受けるので、100人が余裕で収まる大教室で行われます。ドラマなどで見る大学っぽい授業は、専門科目の方が近いと思います。大学生感があるという意味で新鮮味があり楽しいですが、教室が広い分、先生とのコミュニケーションは取りづらく、双方向というより一方向の授業になりやすいため、しっかりと意識して聞く必要があります。ただ、分からないところや疑問を持ったところの対処がないわけではなく、サポートはしてもらえます。授業後にはTA(ティーチングアシスタント)の先輩や、先生に相談しやすい雰囲気があるので、困ったことがあればすぐに助けを求めることができます。真面目に質問する学生に対してはどの先生も優しく対応してくださるので、理解できるまで学習できる良い環境が整っていると思います。
卒業後の進路は?
まず、大学院への進学率が85〜90%以上だと言われています。そして割合は少ないですが、学科卒業後に就職する人もおり、化学にまつわる分野以外に就職する人もいます。大学院修了後は化学関連の企業は勿論のこと、あらゆる産業界で広く活躍されているようです。民間企業以外に大学や国公立の研究機関で研究者になる卒業生も多くいます。新素材の開発・応用が盛んであるというトレンドに合わせて、最近の就職先は化学メーカーだけでなく、エレクトロニクス、自動車、医療精密機械、食品、医薬、情報・通信関連などへ広がっているようです。その他に、海外に派遣され共同研究で国際的に活躍する卒業生も、近年増えているようです。このように修了後、多岐にわたる分野で活躍できるのも、化学生命工学科の魅力と言えるでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?化学生命工学科について、前よりも解像度が上がったのではないでしょうか。化学生命工学科は、化学とバイオの両方を学ぶことができる、学問領域が広い魅力的な学科です!高校生のみなさんに化学生命工学科の魅力が少しでも伝われば嬉しいです。この記事を読んで化学生命工学科に興味が湧いた方は、ぜひ一度オープンキャンパスに参加してみてください!拙い文章ではございますが、最後までお読みいただきありがとうございました。
Profile
所属:工学部化学生命工学科3年生
出身地:愛知県
出身校:愛知県立岡崎高等学校