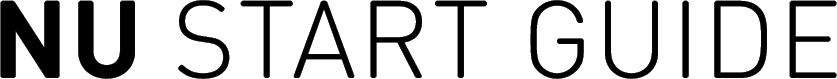2024.12.03
- 大学生活全般
国際会議って何するの?
みなさん、こんにちは!環境学研究科 博士後期課程1年の松山です。学部は名大の理学部地球惑星科学科で、大学院からは環境学研究科の岩石鉱物学研究室に所属しています。
私は今回、スペイン北部・オビエドで開催された7th Orogenic Lherzolite Congress (第7回造山帯レルゾライト会議)という国際会議に参加しました。この記事では、その会議の内容についてご紹介します!将来は国際的な研究に取り組んでみたいという方の参考になれば嬉しいです!また、そのような方が地球惑星科学科に興味をもっていただけるとなお嬉しいです!
①会議の概要
「レルゾライト」とは地球のマントルの上部を占める「かんらん岩」という岩石の一種です。そんなマントルの岩石の名前を冠するこの会議は、世界中の様々なマントル研究者が数年に一度、一堂に会して情報交換を行うために開催されています(ちなみに今回は10年ぶりの開催でした)。欧州を中心に10ヶ国以上から約70名の参加者が集まり、日本からは私を含め4名での参加でした。
②事前巡検
今回の会議のような、岩石を対象とする分野の会議・学会では、ほとんどの場合「巡検」と呼ばれる見学会がセットになっています。この見学会では、開催地に近い有名な(≒よく研究されている)岩石露頭を解説付きで見学し、知見を深めます。また様々な(専門の異なる)研究者が意見交換をすることで研究が発展したり、岩石試料を持ち帰る事で新たな研究が生まれたりもします。
今回は、オビエドからバスで3時間のところに位置するCabo Ortegalという地域を、1泊2日で見学しました。Cabo Ortegalは、ユネスコ世界ジオパークに認定されており、美しい景観と学術的な価値を併せ持つ、世界でも屈指の地域です。解説はオビエド大学の研究グループを中心に行われました。
巡検の2日間は基本的に雨が降っており、霧のせいで景観は楽しめませんでした……(スペイン北部ではよくある天気とのこと)。一方で、見学した岩石はどれも素晴らしく、私もいくつか岩石試料を持ち帰りました。また、巡検の最中や食事の際には色々な人と話すので、知り合いがたくさんできました。

③会議
会議はオビエド大学が所有する歴史的な建物で行われました。映画に出てきそうな雰囲気で、「これがヨーロッパだ!」という感じの講義室です。こういった雰囲気の会場は欧米の方からしても珍しかったようで、みなさん盛り上がっていました。
今回の会期は3日間で、口頭発表が37件、ポスター発表は28件行われました。「マントル研究」といっても、その対象や方法は様々です。岩石の採取場所でいえば、深海底から高山地帯、欧米からアフリカ・中東まで幅広く研究されています。方法でいえば、化学組成、含水量などの物性、大型試験機を使った変形実験などこれまた多様です(ちなみに私の専門は、岩石の変形組織の解析です)。今回の会議でも多種多様な研究成果が発表され、非常に盛り上がりました。
口頭発表は発表15分と質疑応答5分という形式で実施され、ポスター発表はフラッシュトーク(1分での発表紹介)のあとに、2時間の発表時間が確保されました。ポスター発表の時間は発表者以外は自由に見て回ることができるので、活発な議論が随所で行われました。
今回私は、ポスター発表を1件行いました。専門領域が近い研究者もかなり多く参加しており、非常に有意義な議論を行うことができました。初めての国際学会ということもあり最初は少しグダグダしてしまいましたが、一定の成果を得ることができてホッとしました。(余談ですが、この会議で発表した内容が先日、国際論文誌で出版されました。ご興味のある方はぜひご覧ください)
④国際学会に参加する意義
国際会議へ参加することの最大の意義は、海外研究者のコミュニティとのつながりを得られることです。私が専門とする地質学の分野では、研究対象・研究方法が多岐にわたるため、“全く同じ専門性を有する”研究者の数は非常に限られています。そういった背景から、大きな研究プロジェクトを実施するときには国や年代の垣根を越えてメンバーを集め、協力して研究を進めます。この共同研究は国内の研究コミュニティでも同様にして行われますが、国際的なコミュニティではより壮大なプロジェクトが行われたり、研究者の多様性が大きいプロジェクト設立の機会が多かったりします。プロジェクトのメンバーを集めるときには、やはり“知り合い”の研究者から声をかけていくことがほとんどであり、全く面識のない人にいきなり声をかけるというのは非常に稀なケースです。ですので、自身のキャリア形成・能力醸成のためのみならず、日本の研究コミュニティが世界でも存在感を発揮していくためにも、今回のような国際会議に積極的に参加していくことが非常に重要です。
また同様に、このような国際会議では参加者の専門性の多様性が大きいことから、本当に多種多様な研究発表を聴講することができます。「“学ぶ”の語源は“真似ぶ(まねぶ)”だった」という説話もあるように、普段の国内学会では目にしないような対象・方法・結果を見て学び、“真似ぶ”ことで、自分自身にしかできない独創的な研究が生まれる可能性もあります。この観点も、自身の成長につながるだけでなく、分野全体の発展を加速させる側面を持っているという点で、非常に重要です。

⑤おわりに
今回は、“学術的な国際会議”に着目した記事を執筆させていただきました。国際会議への参加についてまとめると、「自身の成長につながるだけでなく、日本の研究コミュニティ・分野全体の発展にも貢献しうる」というのが私の考えです。これは国内の学会や研究集会を軽視しているということではなく、海外研究者とのコミュニティも非常に重要である、ということを再度強調させていただきます。
名古屋大学の理学部地球惑星科学科は、全国初の地球科学科として1949年に創設された歴史ある学び舎です。“諸惑星との比較から地球を捉え、過去・現在・未来の状態を解明する。”というテーマを掲げながら、地球環境システム学、地質・地球生物学、地球化学、地球惑星物理学、生態学の5大講座を中心に、地球史学や大気水圏科学に至るまで、地球で起こる様々な現象を広く・深く研究しています。
“地球”の研究に興味がある方、国際的な研究活動に興味がある方、この記事を読んでみて地球科学が気になった方、みなさまの参考になっていれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました!
Profile
所属:環境学研究科博士後期課程1年生
出身地:愛知県
出身校:名古屋市立向陽高等学校(国際科学科)