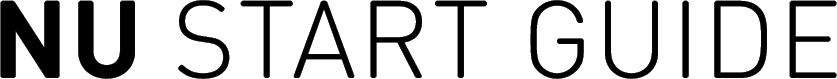2025.10.20
- 大学生活全般
名大で目指す博士号取得: メイク・ニュー・スタンダード次世代研究事業
みなさん、こんにちは!環境学研究科 博士後期課程2 年の松山です。学部は理学部地球惑星科学科の出身で、大学院からは環境学研究科の岩石鉱物学研究室に所属しています。
今回は、名古屋大学が展開する博士後期課程学生向けの支援事業「メイク・ニュー・スタンダード次世代研究事業」を紹介させていただきます。
大学受験で志望校を決める時には、自身の将来目標を見据えて志望校選びに取り組む方も少なくないと思います。私は高校時代から研究者になることを志していましたが、実際にその目標を叶えるためには何が必要なのか、どのような大学(大学院)生活を送ることになるのか、よく分かっていないまま「地元だから」という理由で名古屋大学を第一志望校としていました。
かつての私のように「将来は研究職に就きたいが、具体的なプランは描けていない」「どのような基準で志望校を選べばいいのかわからない」といった方の参考になれば幸いです!

博士号とは
博士号(はくしごう)とは、大学で交付される最も高いレベルの学位で、英語ではPh.DやDoctor's degreeと呼称されます。日本では学識の豊かな人を比喩的に〇〇博士(はかせ)と呼ぶことがありますが、学問の世界では博士は博士号という資格を有する人、もしくはその資格そのものを指します。
大学で得られる学位には、以下の3つがあります。
・学士号(Bachelor):大学の学部において、単位を取得して卒業することで得られる学位。
・修士号(Master):大学の学部を卒業後に大学院に進学し、博士前期課程(修士課程)において単位を取得し、修士論文の提出・審査を経て課程を修めることで得られる学位。
・博士号(Ph.D, Doctor):博士前期課程の修了後、博士後期課程(博士課程)において単位を取得し、査読有りの学術雑誌に研究論文が掲載され、博士論文の提出・審査を経て課程を修めることで得られる学位。
学士号<修士号<博士号の順に取得要件が厳しくなり、資格としての専門性も高くなります。博士号という資格は、その専門分野において研究の成果や能力を(世界的なレベルで)認められたことの証明であり、現代では大学教員になる上でほぼ必須の要件になっているほか、民間/公的研究機関においても重宝されています。
博士号を取得するには
ここでは、本学の環境学研究科における課程博士(理学)を基にした博士号取得の流れを紹介させていただきます。取得方法は専門や大学、国によって異なるので、あくまで参考例として読んでいただければ幸いです。
博士号を取得するには、大学の学部を卒業後、まずは大学院に入学します。大学院への入学には入学試験があり、多くの学生は学部3年生の春休み頃から準備を始め、学部4年生の夏休みに受験します。大学院では博士前期課程(修士課程; 標準2年間)を修めた後、博士後期課程(博士課程; 標準3年間)に進みます。
博士前期課程博士前期課程の修了には、講義の受講(単位取得)と学位論文の提出/審査への合格が必要で、学部の卒業(学士の取得)とは異なり一定の研究実績を認められる必要があります。さらに博士後期課程の修了には、講義の受講と学位論文の提出/審査に加え、筆頭著者としての査読付き国際論文誌への論文掲載が必要となるので、修了のハードルはぐんと高くなります。

博士学生を取り巻く環境
博士学生(博士後期課程の学生)の本分は大まかに「講義の受講」と「研究活動」の2つですが、研究活動の内容は多岐に渡ります。研究の核となるフィールド調査や分析・実験にはじまり、取得したデータの整理・解析、先行研究の読み込み、研究室のセミナーや学会への参加・研究発表、その研究の“ゴール”にあたる論文の執筆・投稿などが挙げられます。自身の研究を論文として発表するには、その研究がまだ誰も明らかにしていない内容である必要があるため、研究活動は常に「手探りで洞窟を掘り進める」ような感覚を伴います。没頭してぐんぐん進むこともあれば、自分の現在地を見失って立ち止まってしまうこともあります。
しかしながら、多くの博士学生を苦しめるのはこの研究遂行上の困難ではなく、経済的問題とそれに伴う心理的ストレスだと私は考えています。日本では博士学生はあくまで「学生」なので、日々の生活費に加え大学院の授業料を支払う必要があります。博士後期課程に入学するのは通常24歳〜なので、この頃には多くの同級生は就職し、お給料を稼いでいます。その一方で、自身は授業料を払いながら「学生」を続けているという状況は、博士号の価値が浸透していないという社会的状況も相まって、大きな心理的負担となることが多いです。この状況を打破するためにパートタイムの仕事に就く博士学生もいますが、その場合には研究の時間が減ってしまうため、自己管理とバランス調整が重要になります。
これに加え、研究を進めるには、調査や分析、学会参加や論文投稿のための「研究費」も必要になります。研究費については指導教官(研究室の先生)が拠出してくださるケースがほとんどではありますが、その場合には研究費の使途や額面が制限されるため、やはり自分自身の研究費を持ちたいという人がほとんどです。しかし研究費を獲得するには、優れた研究計画書を準備し、研究費の公募に応募して競争に勝つ必要があるため、この過程でも精神がすり減らされていきます。
名古屋大学の博士学生支援:概要
そこで本学では、博士学生に経済的支援を行うことで研究に専念できる環境を用意する「東海国立大学機構メイク・ニュー・スタンダード次世代研究事業」が展開されています(公式HP:https://dec.nagoya-u.ac.jp/spring_information)。同事業に採択された学生は、学生であると同時に研究者でもあることからRESEARDENT(RESEARcher + stuDENT)と呼ばれ、月額180,000円の研究奨励費、年間250,000円の研究費が支給されます。このほかにも、大学院授業料の一部免除、国際学会等への参加のための海外渡航支援、専門の異なる博士学生やメンター等との交流会の実施など、「さまざまな形態で将来の社会に貢献する博士人材の育成」のための支援が充実しています。
本事業に採択されるには書類審査と面接審査を合格する必要があり、簡単な道とは言えません(年間およそ200名を採用)。しかし、日本学術振興会(JSPS)が全国展開する博士学生向けの制度(特別研究員DC1)の2025年度採用者数が全国で708名(採用率14.3%)であったことを踏まえると、同事業の存在が本学の博士学生にとって“強い味方”であることは間違いありません。
名古屋大学の博士学生支援:実体験
私自身も、2024年度に同事業に採択され、1年間の支援をいただきました。ここでは、実際に私が体験した同事業の活動についてご紹介します。
同事業が主催する1泊2日のBoot Camp(https://dec.nagoya-u.ac.jp/phd-mns/activity/146.html)では、専門と国籍が異なる初対面の4人でチームを組み、融合・共同研究について議論を深めました。最初は言語の壁や価値観の違いにお互いが苦戦しましたが、食事の時間などを通じて打ち解け合い、最後には洗練されたプレゼンテーションを行うことができました。このときのメンバーはもはや “戦友”ともいえる存在で、1年が経った今でも、メッセージのやり取りなどをしています。
さらに私は同事業の支援を受け、アメリカ・ハワイ島で4泊6日の地質調査を実施しました。外国における単独調査は初めてだったので不安もありましたが、この挑戦によって海外渡航に対して前向きになり、とても良い経験になりました。
また同期間には、経済的支援による私自身の“心の余裕”も幸いしたのか、2編の論文が国際誌に掲載されました。もちろん、この論文の出版は、指導教官を始めとする様々な方の協力があったからこその結果ですが、私にとっては「心配事を減らして研究に打ち込むこと」の重要性を身に染みて感じる出来事になりました。
まとめ
今回は、“名大で目指す博士号取得”をテーマに、博士学生の実態や本学の支援体制を紹介させていただきました。日本では、先述の通り博士号の価値があまり浸透しておらず、“アラサーの学生”である博士学生に対する社会の見方も非常にシビアです。
実際、日本における修士号・博士号の取得率は、アメリカや英国、ドイツなどの欧米諸国と比べると半分程度(もしくはそれ以下)に留まっています。例えばフランスでは、博士学生は大学と雇用関係にあり、給与を受け取りながら研究に従事しています。もちろん授業料の支払いはなく、社会保険も整備され、一般社会でも学生ではなく“社会人”として受け入れられています。このように先進的な諸外国と我が国との差は歴然としていますが、名古屋大学の博士学生支援は、本学の教育目標「勇気ある知識人の育成」を良く体現した、国内屈指の制度であると感じています。博士号取得に興味がある方、将来は研究職に就きたいという方は、ぜひ本学をご検討ください。
最後までお読みいただきありがとうございました!
Profile
所属:環境学研究科博士後期課程2年生
出身地:愛知県
出身校:名古屋市立向陽高等学校(国際科学科)