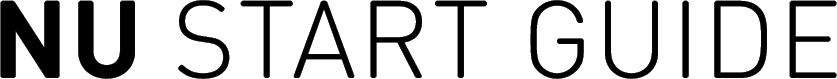2024.09.27
「高校地学」選択者のあれこれ
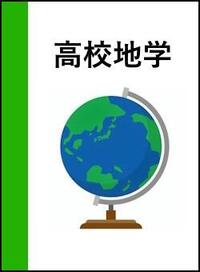 みなさん、こんにちは!環境学研究科 博士後期課程1 年の松山です。名古屋大学理学部地球惑星科学科を卒業し、大学院からは環境学研究科に所属しています。
みなさん、こんにちは!環境学研究科 博士後期課程1 年の松山です。名古屋大学理学部地球惑星科学科を卒業し、大学院からは環境学研究科に所属しています。
私は高校2年生から「地学を学べる大学へ進学したい!」と思い、最終的には理科2科目を化学・地学で受験し、名古屋大学の理学部へ進学しました。この記事では、そんな「高校地学」を選択した場合の受験?大学生活のあれこれを紹介していきます。地学が好き、大学で地学を学ぶことに興味がある、という方の参考になれば嬉しいです!
①「地学」選択の背景
私が通っていた高校では、1年生で生物基礎、2年生で物理基礎・化学基礎が必修、3年生では化学が必修で、もう1科目を物理・生物・地学から選択する形式でした。ですので、カリキュラム上は地学を選択できるのは3年生だけ(※地学基礎は履修できない)でした。
大学で地震について学びたかった私は、2年生の秋から地学基礎の教科書を読み始め、3年生で地学を履修することに決めました。この時、クラス担任の先生と地学の先生からからは「お前は地学で飯を食っていく覚悟があるということだな?」と、決意を確認されました。当時は「あります」と呑気に答えたものですが、振り返ってみるとこの選択は人生において非常に大きな決断だったと感じます。また私の学年では地学履修者は私1人だけでしたが、それでも地学の授業を開講してくださいました。本当にありがたいことだったと思います。
②「地学」の授業と受験勉強
 授業は地学実験室や準備室で先生と1対1で行われ、4~7月のほとんどの時間は先生と教科書を読み進めながら、ワーク演習を行いました。授業は週に3~4回のペースでした。地学は共通テスト(※当時はセンター試験)・2次試験ともに、知識ベースの問題が非常に多く、用語に関する正誤判定問題や重要事項の記述解答問題などが頻出します(個人的には、生物の問題と似ていると感じています)。この傾向に対応するため、用語の定義、用語説明の重要ポイントを網羅的に学びました。また地学の大きな特徴として、”地質図”の判読問題が頻出します。中学理科で学ぶ「地形図とボーリング調査の柱状図」問題の発展形だと思っていただければ大丈夫です。中学理科の中でもこの問題が非常に苦手だった私は”地質図”でも大苦戦しており、重点的に教えてもらいました。
授業は地学実験室や準備室で先生と1対1で行われ、4~7月のほとんどの時間は先生と教科書を読み進めながら、ワーク演習を行いました。授業は週に3~4回のペースでした。地学は共通テスト(※当時はセンター試験)・2次試験ともに、知識ベースの問題が非常に多く、用語に関する正誤判定問題や重要事項の記述解答問題などが頻出します(個人的には、生物の問題と似ていると感じています)。この傾向に対応するため、用語の定義、用語説明の重要ポイントを網羅的に学びました。また地学の大きな特徴として、”地質図”の判読問題が頻出します。中学理科で学ぶ「地形図とボーリング調査の柱状図」問題の発展形だと思っていただければ大丈夫です。中学理科の中でもこの問題が非常に苦手だった私は”地質図”でも大苦戦しており、重点的に教えてもらいました。
夏休みは、ワークを解き進めながら、センター試験の過去問題(赤本)演習を行いました。この勉強は、いままでに学んだ知識の確認にはうってつけで、受験に向けた基礎固めとなりました。
夏休み明けの9~11月は、2次試験レベルの問題演習を行いました。様々な大学の地学の過去問題を家で解き、先生に解説してもらうという形式です。ほとんどの問題は用語に関する記述説明や地質図判読に関する問題ですが、しばしば高校物理の知識を利用する問題があるため(例えば、宇宙の広がりに関する問題で万有引力とドップラー効果を利用する問題など)、この演習では対応力の幅を鍛えました。
12月からは他の理科科目と同じで、センター試験の過去問題やワークの解き直し、センター試験受験、受験校の2次試験対策と進めました。地学は大手予備校でもほとんど授業がないため、基本的には自分自身で勉強し、困ったときに学校の地学の先生に聞く、というスタイルで勉強していました。
③「高校地学」選択の有利不利: 受験編
高校地学を選択していて有利だった、と感じた場面は、私の場合はあまり多くなく、有利があっても何かしらのリスクが付随していたように感じます。
例えばセンター試験(共通テスト)では、知識ベースの問題が多いため、物理や化学と比べると計算ミスのリスクが少ないです。また用語も生物と比べれば少ないので、勉強コスパが良いという人もいます。一方で、「地学」の受験者数は物理・化学・生物に比べると圧倒的に少ないため、全国平均点が低くても得点調整が行われないことがほとんどです。私の体感では、平均点が低い年(他科目に対して-15点など)の問題はやはりそれなりに難しく、受験した年もそのような事態にならないことを祈って過ごしていました。
2次試験では、用語の説明問題は単純である一方、風の動きや宇宙の広がりなど物理(力学)の数式を用いる問題があり、「物理」の勉強もそれなりに必要となります。この点では、物理+地学が最も効率の良い組合せなのですが、(私の母校も含め)化学が必修であることが多いのが難点です。
④ 「高校地学」選択の有利不利: 大学入学後編
名古屋大学理学部では、学部1年生向けの地学の授業は計3つ開講されています。どの授業も、当然「高校地学」未履修者向けの内容なので、知識の幅という点では有利に感じました。
理学部の定員は270人で、2年次から学科に配属されます。地学を学ぶ地球科学科に進学できるのは25~28人と限られており、全体の1割程度です。そういった状況の中でも、高校地学を履修していた学生は0~2人とさらに限られています。私の学年ではたまたま3人いましたが、先生方もかなり驚かれていました。学科に入ってからの授業は、2年生では1年生での基礎知識を基に、3年生以降はそれまでの講義内容を基に講義が行われるので、高校地学の履修による有利はあまり感じませんでした。一方で、地球科学は他の分野の知見を総動員して研究を進めるので、2?3年生では数学や物理、化学や生物の授業がたくさんあります。ですので、学科に進学した後は、高校地学の履修よりも苦手な科目がない方が有利になると感じました。
4年生になると研究室に配属されますが、ここまでくると高校地学の履修の有無はほとんど関係ありません。研究室に入って卒業研究を始めると、好きなこと・得意なことがあると楽しいです。私の友達は、動物が好きで鳥の生態を研究していたり、化学と宇宙が好きで隕石の研究をしていたりします。私自身は、2年次の野外実習で「野外調査で岩石を見るのも好きだ!」と気づき、野外で採取した岩石を使った地球内部の地震波に関する研究をしています。「野外調査がなんだか楽しそう!」という理由で地球惑星科学科に入る人も多いですが、いざ卒業研究となると、みんな積極的に頑張っている感じです。
⑤おわりに
今回は、高校地学の履修というテーマで、理学部地球惑星科学科のあれこれを紹介させていただきました。高校地学の履修についてまとめると、「有利なことも確かにあるが、他の科目を履修していないということで不利に感じる場面も多々ある」というのが私の考えです。むしろ、地球惑星科学科でさえも高校地学の履修者はほんの数人で、大学1年生の講義で地学を学び始めた人がほとんどです。
名古屋大学理学部の地球惑星科学科は、地球科学を全般的に学べることが特徴です。野外実習も多く、2年生の終わりには全員が13泊14日の「地質調査」を経験します。5-6人の班で一緒に調査を行う2週間は、かけがえのない経験になること間違いなしです!
地学に興味があった方も、この記事を読んで地学が気になったあなたも、楽しさ満点の地球惑星科学科をぜひ検討してみてください!
Profile
所属:環境学研究科博士後期課程1年生
出身地:愛知県
出身校:名古屋市立向陽高等学校(国際科学科)