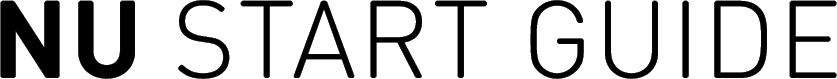2024.10.03
過去問攻略!
皆さんこんにちは。工学部の長尾です。
この文章を読んでくれている受験生の皆さん、模試や定期試験に忙しい時期かと思います。いつもお疲れ様です。
 さて、高3生向けの話になりますが、「過去問」はもう解いてみましたか?
さて、高3生向けの話になりますが、「過去問」はもう解いてみましたか?
まだできていないという方は、まずは直近5年くらいの過去問から、適当なものを1年分解いてみましょう。遡りすぎると出題傾向が乖離してしまうので、5年くらいが良いと思います。
出題傾向の変化とは、例えば2017年以前の名大英語は自由英作文ではなく英文和訳になっている、などの事例です。とりあえずは近い年から解くのが無難ですね。
では、過去問演習の効果を生かし、力をつけるにはどうしたら良いのでしょうか?
今回は過去問の解き方や振り返り方を考えてみましょう。
1) 過去問を解く目的
過去問を解く意味は、大きく分けて2つあります。
1つ目は本番の形式に慣れること。
2つ目は出題傾向を研究することです。
一つずつ解説していきます。
1-1 本番に慣れる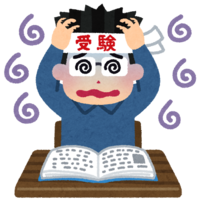 まずはまとまった時間をとって、1科目の1年分の問題を所定の時間で解きましょう。できれば本番通りの時間割で全科目を解きたいですが、時間の余裕が無ければ1日1科目ずつで良いです。それぞれの科目の問題数、時間配分、解答形式(以下出題様式とする)を頭に入れましょう。また、氏名、受験番号記入の時間も加味しましょう。大きめの紙を用意して、実際の解答用紙を再現しても良いですね。
まずはまとまった時間をとって、1科目の1年分の問題を所定の時間で解きましょう。できれば本番通りの時間割で全科目を解きたいですが、時間の余裕が無ければ1日1科目ずつで良いです。それぞれの科目の問題数、時間配分、解答形式(以下出題様式とする)を頭に入れましょう。また、氏名、受験番号記入の時間も加味しましょう。大きめの紙を用意して、実際の解答用紙を再現しても良いですね。
ある程度(5〜10年分くらい)過去問を解くと、出題様式が分かってきます。すると、カタカナで解答するところをひらがなにしてしまった、時間が足らず簡単なところを解けなかった、などの初見でありがちなミスは防げるようになります。
1-2 研究と対策をする
さて、ここまでこなせたら、次は出題傾向の研究です。たくさんの問題を解いて、大学が求める知識や発想を吸収しましょう。ここではとにかく解くことが必要なので、無理に1年分まとめる必要はありません。1問ずつで良いので、余った時間を活用して柔軟に進めていきましょう。
ところで、一般に過去問傾向から出題が予想される分野は、重点的に対策するべきです。ただし、ネットの不確かな情報を頼りにしないようにしましょう。また、必ず出題されるとは限りません。全範囲を網羅した上で、余裕があれば取り組む程度で充分です。
2) 効果的な振り返り方
過去問を解いた後の振り返り方についてです。
今回は2点に絞ってお伝えします。
1つ目は、解き直しする必要があるか、するならいつするかを決めること。
2つ目は、出来なかった箇所を確認し、どう対策したらできるようになるか考えることです。
2-1
同じ問題を繰り返し解くことも大切ですが、入試では初見の問題ばかりです。できなかった問題は何回解き直すのか、できた問題は何回見直すのか、ある程度自分でルールを作った上で効率よく進めていくべきです。
2-2
出来なかった箇所は模範解答や解説と何度も見比べて、原因を探りましょう。計算ミス?見落とし?知識不足?しっかり間違いの理由を探すだけで、大きな力になるはずです。更に、どんな勉強をすれば次回出来るようになるかを考えて、実行しましょう。単語が分からなければ、単語帳。計算ミスなら演習という具合です。
自分の間違いの傾向が分かってきたら見直しは簡単に済ませて、復習に時間をかけると良いですね。
以上が過去問演習の取り組み方です。ご参考にしていただければ幸いです。
Profile
所属:工学部機械・航空宇宙工学科1年生
出身地:愛知県
出身校:愛知県立瑞陵高等学校