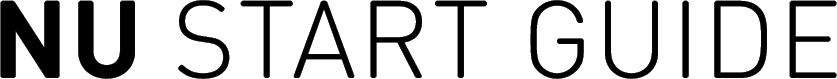2024.10.08
共通テスト対策について
こんにちは!経済学部2年の福井です。最近、少しずつ涼しくなってきましたね。季節の変わり目は体調を崩しやすい時期でもあります。生活リズムを整えるようにしましょう!今回は、共通テストの勉強方法や私が受験した科目ごとのポイントについて紹介していきます。
●共通テスト対策いつからする?
共通テストに向けた勉強は、いつからどのようにやっていけばいいのか?この答えは、その人の志望校の二次試験との配点比率や成績状況によって変わってきますが、今回は私の例で紹介します。当時は下のような状態でした。
・共テ:二次=900:1500
・二次の科目は国語、数学、英語
・二次試験より共テのほうが苦手
 10~11月は、勉強の割合的に言えば共テ1割、二次9割でした。途中から共テ模試、記述模試、オープンなどの模試もあって復習に追われ自分の勉強があまりできない時期もありましたが、ほとんどは二次試験対策をしていました。
10~11月は、勉強の割合的に言えば共テ1割、二次9割でした。途中から共テ模試、記述模試、オープンなどの模試もあって復習に追われ自分の勉強があまりできない時期もありましたが、ほとんどは二次試験対策をしていました。
12月からは、共テ8割、二次2割くらい。第3回の模試が共通テストのボーダーに少し届かないくらいだったので、共テの勉強の割合を大幅に増やしました。また、学校でも共テ対策が始まりその復習をしていたためでもあります。このときの二次対策は以下のように進めていました。
国語:現・古・漢それぞれ一週間に一回は記述問題に触れる
数学:記述用の問題集を先生に添削してもらう(頻度としては2〜3日に1回)
英語:一週間に一回以上長文に触れる
●共通テスト対策方法
 共通テストを対策するとなったとき、基礎固めなどが終わった段階では下の3つの手順があると思います。それぞれの手順のポイントについて説明します。インプットは一通り終わったとしています。
共通テストを対策するとなったとき、基礎固めなどが終わった段階では下の3つの手順があると思います。それぞれの手順のポイントについて説明します。インプットは一通り終わったとしています。
①共通テストの解き方を学ぶ
どの教科も思考力などが問われるため、形式に慣れていないと解くことが大変です。どんな風に解けばいいのか分からない科目については、解き方を説明した参考書などを活用して攻略法を掴むと良いです。私は共テのリーディングが苦手で、長文の読み方を知りたかったのでこの科目だけ参考書で対策していました。模試などで、ある程度慣れて解き方が掴めているという人はこの手順はやらなくて大丈夫です。
②予想問題を解く or 過去問を解く
共テの問題の進め方が分かったら、演習を進めていきましょう。ここでは予想問題か過去問、どちらを解いても大丈夫です。私は、予想問題をベースに演習を進めて、現代文の小説や数学のデータの分析といった、自分の苦手な分野を過去問で解くという進め方をしていました。
③復習をする
演習をしたら、採点したあとすぐに復習しましょう。全てを復習する必要はないので、解けそうで解けなかった問題を中心になぜ間違えたかを分析していきます。その後、リーディングは音読をして、リスニングはシャドーイングをしていました。どちらも意味をしっかり捉えながら行うことが大切です。数学は、解説を見た直後に自力で解けるかチェックしていました。理科基礎・社会に関しては、教科書や参考書の該当部分を見返して、知識を入れ直していました。演習で知った新しい知識をいつも確認するものに書き込んで情報を一元化しておくと、復習がスムーズになるのでおすすめです。このあとは、②③を繰り返していきます。
●共通テストの各科目のポイント
◯国語
国語は、1問の配点が高いことが特徴です。また新課程から現代文の大問が増えたことでより解く時間がなくなることが予想されます。
先に問題を読んでおくと、どの部分でどのように問われるかを把握でき、スムーズに問題に移ることができるのでおすすめです。
◯数学
計算ミスには要注意です!特に確率や微分・積分の分野では最初に間違えると、関連する問題全てを間違えることもあります。上記の分野に関わらずですが、大問の最初の問題は落ち着いて解く、一度見直すなどの工夫をしましょう。ある分野が苦手…という人は、分野ごとに過去問を活用するのがおすすめです。例えば、確率が苦手だという場合は、確率の大問のみを遡って解いていくというような感じです。時間を決めてその分野だけ対策して慣れていきましょう!
◯英語
リーディングについては、近年分量が増える傾向にあります。今年度の問題がどうなるかはわかりませんが、時間的に厳しい戦いになるでしょう。その中で得点するには、解けるところを解く、解けないところを飛ばすといった判断が大切です。普段、演習するときから時間配分を大体決めておいて、時間になったら迷いなく飛ばす練習をしておきましょう。また、苦手な大問の形式が分かっていれば、その大問を最後に解くなどの優先順位をつけることもおすすめです。私は、複数の文章を読む形式や時系列問題、内容一致問題の得点率が低かったため、それらで構成されていた大問の順番を最後にしていました。
リスニングについては、前半の短い音声の問題をまずは正確に解けるようにしましょう。それができるようになったら、1回で短い音声の問題を解けるようにします。そして余った時間で後半の1度しか読まれない長い音声の問題を先読みしていきましょう。先にイラストやキーワードを見ておくことで、リスニングのときに単語を拾いやすくなります。また、演習する際は1.25倍速で聞くようにすると本番にゆっくり聞こえるようになるので、リスニングが得意な人はぜひやってみてください。
◯日本史
教科書だけで勉強していると、年代の並び替えが対応できません。年代の並び替えが苦手な人は問題を解いて、資料集などの年表を見ながら覚えていきましょう。また、共通テストでは史料の問題がよく出題されます。情報を読み取ることができれば正解できる問題もあるので、演習をして慣れておきましょう。
◯倫理・政治・経済
新課程では、こちらの科目はないので省略します!
◯化学基礎
暗記する事項は限られているので、しっかり覚えきりましょう!計算問題については、どの分野も必ず解けるようにしておきましょう。
◯生物基礎
教科書に載っているところは必ず覚えましょう!(注釈だとしても覚えていきましょう。)化学基礎に関しても言えることですが、50点分しかないためその年によって出題される分野が違うこともあります。苦手な分野があれば、特に重点的に勉強しておきましょう。
以上が、共通テスト各科目のポイントになります。自分の伸びしろや配点なども加味して、どの科目にどれくらい対策の時間をかけるか考えていけるとよいですね。
Profile
所属:経済学部2年生
出身地:愛知県
出身校:愛知県立豊橋東高等学校