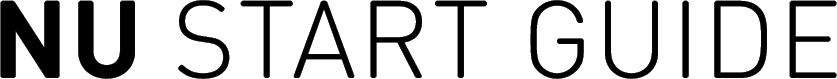2025.08.19
模試の活用方法〈完全版!〉③記述模試編
皆さんこんにちは!
今回も、①、②に引き続き、模試の活用方法について解説していきますね。今回が最後のパートになります。
今回は、記述模試の受験後について、ポイントをご紹介していきます。
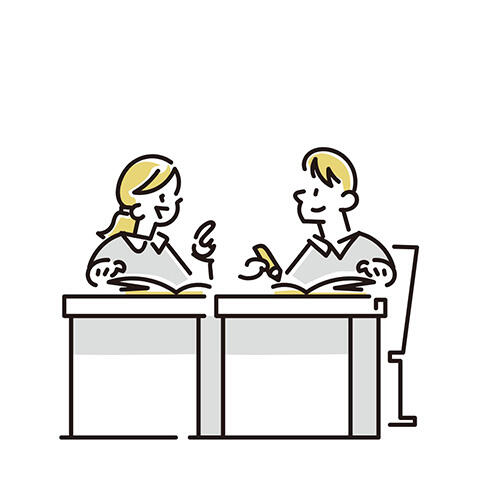
共通テスト模試を受けた後にするべきこと
受験後にするべきことは、次の4つです。共通テスト模試と流れは変わりません。
ただポイントが少し違ってくるので、その点について説明していきますね。
▶自己採点
▶復習
▶分析
▶学習計画を立てる
自己採点
記述模試の自己採点は、共通テストより難しいです。なぜなら、記述問題があり、点数をずれなくつけることが難しいからです。そのため、共通テスト模試ほど正確性を重視する必要はありません。記述問題については、模範解答と自分の答案を見比べ、必要な要素が入っているかを確認してください。そこから復習につなげていけば大丈夫です。
復習
共通テスト模試は、直後に復習することをおすすめしました。記述模試も直後に復習することは同じです。こちらの復習方法は共通テスト模試と同じで、間違えた問題をなぜ間違えたのかを確認、解きなおしをしていきましょう。
それに加えて、記述模試は、添削された答案が返却されたタイミングでもう一度復習することをおすすめします。記述問題の答案がどれくらい点数をもらえていたのか、しっかり確認しましょう。特に、自由英作文などは自分では添削が難しいため、どのように評価されているのかを見ておくとよいですね。
分析
分析についても、模試受験直後に課題を見つけましょう。そして、成績統計資料をもらった後にもう一度分析をしましょう。ただし、ここで気を付けてほしいことがあります。
それは、志望校の出題傾向です。国公立大学を受ける人なら、みな同じ問題を受ける共通テストとは異なり、二次試験は大学によって傾向が大きく違います。
模試で点数が取れなかった分野でも、特に志望校で出やすいところを重点的に行うなど優先順位をつけていきましょう。例えば、名大の文系数学であれば、私の受験時代は、苦手な確率が出やすかったためそこを重点的に演習しました。

【コラム】志望校の出題傾向を知るには?
傾向を知るためには、過去問を解いてみる・塾などの解答速報を見てみるという方法がおすすめです。過去問については、今の時期はそこまでしっかりと解く必要はありませんが、夏休み中に1年分くらいは解いてみて、自分の立ち位置を知ってみるとよいでしょう。また、赤本の最初のほうにある出題された分野や対策方法も参考になるので、ぜひ活用してみてくださいね。
学習計画を立てる
復習・分析をした結果をもとに、次の模試に向けた学習計画を立てていきます。二次試験の科目については、どれもバランスよく勉強していきたいところですが、特に伸ばしたいと思っている科目・分野に時間を割いてみるなどの配分を考えていきましょう。そして、ゴールから逆算していく形で、やるべきことを書き出していけるとよいですね。
以上が、模試の活用方法になります!受験生の皆さんは、共通テストまで残り半年を切りましたね。夏休み明け以降、特に模試が多く復習も大変になってくると思います。今のうちから、自分なりの復習スタイルを確立できると秋以降も効率的に勉強が進められると思うので、頑張ってくださいね。
Profile
所属:経済学部経営学科3年
出身地:愛知県
出身校:愛知県立豊橋東高等学校