2月16日④
JICAエジプト事務所からは、夕食会場に直行です。ナイル川に面した川床のようなお店に、同窓会のメンバーが招待くださいました。
昨日お会いできなかった重要人物であるアフマド・モハメド・ファラハート先生がメインホストでした。ファラハート先生はカイロ大学工学部の教授で、以前は高等教育省の高官であったとのこと、エジプトでは大学の教員が政府に関わるのが普通だそうです。写真、私の向かって左隣がファラハート先生になります。

ナイル川を行き来する観光船を見ながらの会食、例によって炭酸飲料、またはノンアルコールビール、時間も1時間ほどでお開きとなりました。
二泊五日のエジプト出張もこれで終わり、明日には帰国の途につきます。
2月16日③
大使館に引き続いて、渋滞の中、カイロの中心部へと戻ってきて、JICAエジプト事務所への表敬訪問を行いました。到着が遅れて申し訳ありませんでした。
JICA側は海老澤陽所長、矢崎仁太郎次長、島津杏奈さんらにご対応いただきました。会談では、とくに人材交流を焦点に、まず我々の取り組みを紹介、そしてJICAがエジプトで展開する様々な教育プログラムについて教えていただきました。
その中で、これまでは高校への支援をしていたそうですが、最近、高専を作って、そこでの教育を日本からの人材と現地の共同校長という形で進めていくように方針転換をしたというのが興味深かったです。高専機構と連携しているのだそうですが、本学のOBが豊田高専などの校長を務めた実績があることをお伝えしておきました。高専はモンゴルやベトナムなどアジア諸国でも大人気です。
また、JICAも加わってオールジャパン体制の支援で設立されたエジプト日本科学技術大学E-JUSTについてもご説明いただきました。設立わずか15年ですが、すでにランキングではカイロ大学を抜いたとはびっくりです。この大学の研究担当副学長には、ロボット工学者でIEEEの会長をされた本学の福田敏男名誉教授が就かれています。
新しい大エジプト博物館の建築にもJICAによる技術協力があり、そして円借款が建設費の半分以上を占めるとのこと、エジプトにおける日本、そしてJICAの存在感は相当なものだと感じさせられました。

2月16日②
カイロ大学の後、お昼は街中の定食屋で取りました。ライスの中に、野菜や豆、パスタがごた混ぜに入っていて、ケチャップベースのソースを自分で味付けして食べる、というエジプト版ファストフード、美味しく、また300円ほどと、とても安かったのでおすすめです。料理名はコシャリです。この店は、元々屋台から始めて、繁盛して今は同じ場所に店を構えるようになったそうです。料理の写真、アップしておきます。

午後は、まず日本大使館に行って、大使に表敬訪問です。大使館は、カイロの南側、少し離れた街にあります。以前は市中心部の雑居ビルを数フロア借りていたとのことですが、10数年前に広い土地を求めて移転、なかなかセキュリティのしっかりした立派な建物でした。
京都出身の岩井文男大使は、これまでイラク、サウジアラビアの特命全権大使を歴任されているアラブのエキスパートです。会談では、古城勇人一等書記官、緒方彩夏三等書記官にも立ち会いいただき、ひとしきり名古屋大学の活動をお伝えして、今後のサポートをお願いしてまいりました。写真は、岩井大使と、名古屋大学側は私、水谷副総長、木村副総長、そして工学研究科の中村教授、松尾教授になります。

ちなみに、本学のエジプト関係の活動ですが、現在留学生が大学院に4名所属、研究活動では、ScanPyramidsのチームとしてミュー粒子を写真乾板で捉えることでピラミッドの透視をやっている理学の森島准教授、ピラミッドの3D構造をドローンで計測している人文学の河江教授、そして中エジプトのアコリス遺跡で発掘を続けている人文学の周藤教授らになります。
2月16日①
本日は、午前中にカイロ大学を表敬訪問いたしました。
カイロ大学についてまず目についたのは、ものすごく立派なドーム型の建物です。入り口はセキュリティが厳しく、車の出入り、人の出入り、全てきちんとチェックされていました。ちなみにホテルも同様です。最近はテロの発生はほとんどない、とのことですが、中東・アフリカの実情が浮かびます。名古屋大学の場合、車はともかく、人の出入りのセキュリティを厳しくするのが非常に難しいですね。
門を入ってすぐの正面が大学本部です。出迎えの方に中を少しだけご案内いただきました。先ほどのドーム型の建物が隣接していて、その内部を見せていただいたのですが、オペラハウスのような作りで、オーケストラピットまで備えていたのにはびっくりです。3000人が収容可能とのこと、伝統のある素晴らしい建物でした。

その後、10時からは大学院教育と研究担当のモハメド・エル-サイード副学長とヘイディ・バユーミー国際関係室長との会談を同じ建物の中で行いました。私から本学とエジプトとの関わりなどについて説明をした後、簡単にカイロ大学についてご説明いただいたのですが、学生数、タンタ大学を凌ぐなんと25万人!凄まじい規模です。
学生の留学、特に送り出しに大変興味があるようでしたが、ただ、まだまだ経済的には厳しい学生が多く、授業料免除の可能性や、渡航費・滞在費の補助についてだいぶ気にされていました。授業料については協定を結べば相互に不徴収にできること、また渡航費・滞在費についてはJASSOやJICAの奨学金があるということをお伝えしておきました。併せて本学の短期日本語教育プログラムNUSTEPや3ヶ月から9ヶ月の英語による滞在プログラムNUPACE、工学研究科が行っている自動車工学のサマープログラムNUSIPなどについて紹介しておきました。
本学の修了生で同窓会の代表幹事、ザヘル先生が工学の教員をされていらっしゃるので、そのあたりから連携を深めていくのが良さそうです。今回の訪問にもお付き合いいただきました。カイロ大学とは大学間の学術協定はあるのですが、近年はなかなか実効的になっていないところですので、この機会にアフリカの代表的な大学との交流を進めたいと思います。

2月15日③
総会の後は、同じ建物で階を移して懇親会です。同窓生以外にも学術振興会との研究集会に出席していた学生さんたちも集まり賑やかな会となりました。とはいえ、イスラム教が盛んな国ですから、アルコール類は厳禁、ペットボトルの水に加えて炭酸飲料かジュースでした。同じテーブルを囲んだのは、名大側のメンバーとフセイン学長、そして学術振興会のカイロ研究連絡センターの長澤榮治所長などです。長澤所長は、エジプトの近現代社会経済史がご専門とのこと、今回は参加いただき、ありがとうございました。これからも名大の活動を、よろしくご支援ください。
懇親会は着席スタイルであり、テーブルが大きくて、近くの数人としか話せなかったのは残念でした。料理は前菜に加えて、米料理、メインのプレートには肉が数種類というものでした。フセイン学長とのツーショットをアップしておきます。またアルコールがないからか、実に時間通り、1時間で終了です。

会の終了後は、グループで写真を撮ったり、和やかな雰囲気で終了です。エジプト支部の発展、願っています!
懇親会の後は、一路カイロまで車で移動、道中は市場から買ったという牛や羊などを積んだトラックがたくさん走っていました。
ホテルに着いたら、シャワーだけ浴びですぐにベッドにバタンです。私にとって、土曜日の朝起きてから、46時間ぶりのベッドです。疲れました。
2月15日②
カイロ(ギザ)から2時間以上かかってようやくタンタに到着、大学の宿舎をお借りしてスーツに着替え、少しだけ休憩をとってタンタ大学に向かいました。今回の同窓会支部発足は、日本学術振興会との共催で行った研究集会と合わせての開催になります。そちらの研究集会の方、テーマはスマートエネルギーシステムでした。研究集会には、本学からこれまでエジプトからの留学生を何人も受け入れてきた工学研究科の中村教授や同じく工学研究科の松尾教授も参加され、我々よりも一日前にカイロ入りしています。同窓会の準備で担当の木村副総長、DO室の職員も同様です。
到着時には、当初から1時間遅れで、時間通りに(書いてて変ですよね)研究会が終了する頃でした。当日の朝、突然、研究会のスケジュールが1時間長くなったとのことです。その結果、本来15分の講演がいきなり30分になった、と木村副総長がぼやいていました。ですので、時間通り、1時間遅れ、というわけです。
到着後、30分ほどですがタンタ大学のフセイン学長と懇談しました。水谷副総長と木村副総長も同席です。フセイン学長からはタンタ大学の紹介をいただきました。非常に頑張っていて、13もの大学病院を経営、さらに研究力を強化して大学のランキングを挙げてきているとのことです。学生数を聞いて仰天、13万人とのこと、本学は学部大学院合わせて1万6000人、桁が違います。タンタの人口は60万人だそうですから、人口に合わせた極めて大規模な大学でした。
その後、夕方5時からエジプト支部設立総会です。私からご挨拶を差し上げ、支部長に選ばれたサラ・サルマン先生に認定証と支部旗を贈呈させていただきました。毎回、DO室の職員の方、旗を日本から持参して大変だと思います、ありがとうございます。ちなみにサルマン先生ですが、工学研究科で修士・博士を取得され、現在はアル=アズハル大学の教授・学部長を務めていらっしゃいます。また、副支部長はディア・エルディン・アブデルサッタール・マンスール先生、工学研究科で博士を取得し現在エジプト日本科学技術大学の教授です。代表幹事はアハメド・カマル・アブドエル・ザヘル先生、工学研究科で博士号を取得、現在はカイロ大学の助教授です。
なお、私の挨拶の間に携帯音が大きく鳴ったので、何事かとスピーチを止めたのですが、誰も気にしていない様子。何でこの人今話すのを止めたのだろうか、という感じでした。後で聞いたら、携帯音がなるのはほぼデフォルト、聴衆がフラフラ出入りするのが普通、ということで郷に入っては郷に従え、でした。

2月15日①
関空からイスタンブールまで12時間ほど、そこからカイロまで2時間半ほどで、カイロ空港に到着です。時差の関係で到着は10時半頃でした。道中特にトラブルもなく順調な旅路でした。ただトルコ航空、気流の悪いところを通過するときにシーベルト着用のサインを出すだけでなく、皆が寝ていても情け容赦なくかなりの音量で、トルコ語、英語、日本語で、着用を促す放送がかかるのは少しびっくりです。数回起こされましたが、それでもそこそこ寝られたのはよかったです。
カイロ到着後は、まずは昼ごはんをギザで取りました。ナイル川を挟んで東岸がカイロ、西岸がギザになります。旅行会社のアレンジで窓からピラミッドの見えるレストランでの食事、エジプトに来たという実感が湧きました。
ランチの後は、そのまま90kmほど南に離れたタンタ市に車で移動です。当地にあるタンタ大学のモハメド・フセイン学長が、名古屋大学で博士研究員を9ヶ月程されていた関係で、同窓会の立ち上げのホストを買って出てくれたからです。
カイロ・タンタ間は比較的広い道路があり、途中までは順調でした。ただタンタ市が近づくと、ところどころ渋滞になりました。道にほぼ一切信号機がなく、大きな道にはそれでも歩道橋が数百メートルごとに設置されているようなのですが、歩行者はお構いなしに車の流れの途切れた隙を見つけて横断してくるので、それが渋滞の一因になっているようでした。
またタンタ市に近づいてからの車の経路がなかなか奇妙でした。一度道を間違えたのですが(ガイドさんは決して間違ったとは言わないのもカルチャーかもしれません)、その後なぜかひたすらカイロの方向に戻っていきます。何事が起こったのかと思って聞くと、Uターンの場所を探しているとのことでした。そうです。信号機がないので、車の向きを変えるには、Uターンしかないのです。車の流れを切るような、日本で言うと信号がないため右折(エジプトは車は右側通行なので左折)ができない、ちょっとしたカルチャーショックでした。道を間違えなくても、左折ができないので、とにかく行き過ぎてUターンです。進行方向左側にあるホテルを通り越してはるか先まで行ってUターンで戻ってくるのには本当にびっくりしました。
なおエジプトはとても車が多く、その中で日本車はそれほど見かけませんでした。日産が現地組み立て生産しているとのことで、比較的見かけましたが、トヨタ車はそれより少ない印象です。電気自動車もほとんど走っていないようでした。

2月14日②
午後からは京都に移動、私が京都大学助教授だった時に研究室の教授だった佐藤文隆先生を偲ぶ会に出席しました。
京都大学、特に物理教室では(名古屋大学同様)「先生」と呼ばないので、佐藤さんとここでは書きます。佐藤さんは、当時研究室の大学院生でのちに名古屋大学の教授となった冨松彰さんとの共同研究で、新しいブラックホールを数学的に発見したことでよく知られています。佐藤さんの研究や興味は非常に広範で、宇宙論や宇宙線物理などで顕著な業績を挙げられるとともに、膨大な数の本を執筆されていることでも有名でした。
京都大学では基礎物理学研究所長、理学研究科長などを歴任され、学内運営にも非常に貢献された方です。
本来、この会は2月生まれの佐藤さんの米寿のお祝いを予定していたのですが、昨年9月に逝去されたので、悲しいですが偲ぶ会として関係者が集うものになりました。懐かしい人たちにたくさん会えましたが、佐藤さんと話しをすることができなかったのは本当に残念です。
あらためましてご冥福をお祈りします。
京都駅で行われた偲ぶ会の後は、関西国際空港に向い、夜便でイスタンブール経由、エジプトのカイロへと向かいました。全学同窓会の18番目の海外支部となるエジプト支部設立に立ち会うためです。
2月14日①
土曜日の今日は、極めて忙しい1日となりました。
まず、午前中は豊田講堂シンポジオンホールで行われた日本危機管理医学会の総会で特別講演として「宇宙からやってくる人類の危機」と題して35分の講演を行いました。
内容は、太陽フレアという太陽の爆発現象が引き起こす通信障害や宇宙飛行士などの被曝と、惑星など太陽系小天体が地球に衝突することによる大規模災害についてになります。
特に前者では、現代文明が太陽フレアに対して極めて脆弱であること、また長期にわたる停電など大きな災害となりうる規模の太陽フレアの頻度について名古屋大学宇宙地球環境研究所の二人の若手研究者の研究成果をもとにお話ししました。
一人目が三宅芙沙准教授です。屋久杉の年輪に見られる炭素の放射性同位体の量の急激な上昇が、非常に大規模な太陽フレアによって引き起こされたことを突き止めた研究になります。奈良時代、平安時代などに起きたことを証明し、このような現象はミヤケイベントと世界で呼ばれるようになっています。
二人目が早川尚志助教、彼は古今東西の古文書からオーロラや太陽黒点などの記述を見つけ出し、太陽活動を調べるという研究を進めています。大英図書館に入り浸ってメソポタミアのアッシリア帝国の占星術の記述から、国内を駆けまわって岡崎のお寺の古文書まで、オーロラが世界のいつどこで出現したのか、どのくらいの規模だったのかを推定するという研究は、BBCなど世界のマスコミも注目しています。
後半の小惑星については、米欧そして日本らが協力して進めているプラネタリーディフェンスを中心に説明しました。これは衝突の可能性のある天体、そのうちでも大きいものについて、できる限り全て見つけ出し、その軌道を詳細に計算、衝突の可能性が出てきたら、天体の軌道を変えることを含めて、被害をできる限り小さくする、というプロジェクトです。
実際に、2022年にはDARTという探査機を小惑星ディモルフォスにぶつける実験をNASAが行い、小惑星の一部を破壊し、軌道を変えることに成功しています。映画の世界が本当になってきました。
2月13日
本日、午後に豊田講堂で、英語での大学紹介ビデオ作成のためのビデオ撮りがありました。
豊田講堂に行くと、壇上にものものしい撮影クルーがいて、立ち位置、スーツのボタンの開け閉め、ポーズなどを決め、練習からスタートです。
本学の国際広報室のネイティブ職員にも立ち会ってもらい、発音をチェック、一カ所直してもらって、本番です。1分程度の短いスピーチですから、2、3回撮り直して、すぐにOKをもらい、かかった時間は正味15分程度だったでしょうか。なぜか私の予定を1時間半も抑えていたので、時間に余裕ができて助かりました。
このビデオ撮りで、4年近く前に総長になった直後、日本語版の広報ビデオを同じ豊田講堂で撮影したことを思い出しました。ビデオ撮りに慣れていなかったこともあり、大変だった記憶があります。出来上がりは今でも残っていますが、見るのが恥ずかしいですね。
2月10日
本日は東海機構採用者内定懇談会が夕方、ユニバーサルクラブでありました。
今年4月に採用される事務系や技術系の職員の皆さんと、今年度4月1日より後に採用された方々と、機構長や我々名大の執行部、事務局長や事務部長ら機構の幹部職員らを交えての会になります。
私は皆さんとお話しするだけの予定でしたが、機構長が遅れて到着とのことで、急遽、乾杯の挨拶を差し上げる羽目になりました。私の乾杯の発声後すぐに、機構長が到着、改めての挨拶となり、私の挨拶、完全に上書きされてしまいました。
何人かとお話ししたのですが、すでに立派な社会人経験を積んでいる転職組が比較的多いこと、また岐阜大卒、名大卒で母校に貢献をという方も多く、これからの活躍が楽しみです。前職が某旅行会社の方に、つい、以前その旅行会社からチケットの発給で酷い目に遭わされた「ネタ」を披露したのはちょっと申し訳なかったかもしれません。スペインの空港で「あなたは帰りの航空券を持っていない」と言われた時の衝撃は今でも忘れられません。ただ今ではこうしてネタにできるので、良い思い出となっています。
みなさん、元気で、そして楽しく働いてもらえれば幸いです!
2月8日
2月8日
本日は、年に一度の恒例、全学同窓会関東支部の講演・交流会が東京であり、行ってきました。
あいにく寒波が到来、名古屋でも雪がちらつき、新幹線の遅れが心配されました。結局、新幹線は10分ほどの遅れ、途中小田原あたりはかなりの積雪でした。東京も、雪はやみ始めてはいましたが、そこそこ残っていました。そんな中、なんとか会場の竹橋のKKRホテル東京に、開始直前ですが到着できました。
会場からは皇居が一望できます。今日は雪で白くなっていて印象的でした。写真ではわかりにくいかもしれませんが、アップしておきます。

講演会に先立って、昨年末にご逝去された丹羽宇一郎様のご冥福をお祈りして黙祷を捧げました。丹羽様は、関東支部の初代支部長を務められていらっしゃいました。
続いて私から、名古屋大学のスタートアップについて報告をさせていただきました。ディープテックシリアルイノベーションセンターが展開する全生徒必修のアントレプレナー講義やTongaliのスタートアップ教育・支援など、興味深く聞いていただけたと思います。
今回、なんといっても出色だったのは、医学部の同窓生で、今回参加いただいた濱口元総長の同期生、武藤芳照先生の「高齢者の転倒・骨折・寝たきりを防ぐために〜「ぬ・か・づけ」と転倒予防川柳から学ぶ〜」と題したご講演です。
武藤先生は名大の医学部卒業・大学院修了後は、東京の厚生年金病院で整形外科医として活躍、東京大学教育学部に移って学部長、理事・副学長を歴任、日体大の研究所などを経て、現在は東京健康リハビリテーション総合研究所代表理事・所長をされていらっしゃいます。その間、オリンピックの水泳のチームドクターを務めたり、本当に多才な方です。
転倒防止について、本当に役に立つ内容の講演だったのですが、あらゆるストーリーにオチがついていて、飽きさせず、楽しく、そして実践的な講演は初めてでした。
中身を紹介するととてつもなく長くなりますし、先生の面白さはうまく伝えられないので諦めますが、最後のまとめだけご紹介します。
1. すべる、つまずく、落ちる、2. 転ばぬ先の杖と知恵、3. ヤング・オールド、オールド・オールド、スーパー・オールド、4. 片足立ちを意識する、5. 目、耳、そして脚の衰え、6. 命の水を大切に、7. 誰でもいつでもどこでも転ぶ、8. いいクスリも量が多ければリスクに。この8項目、見事に講演内容のまとめになっているとともに、それぞれの文頭の文字を続けると、「すこやかめいだい=健やか名大」、最後までオチがついていました。すごいですよね!
講演の後は、交流会ですが、その前に中村利雄支部長から名古屋城関連の貴重な書籍を寄贈いただいたことに対して、総長として感謝状の贈呈をいたしました。名古屋城は国宝1号ということで、戦争で消失する前に、写真や図面が記録としてきちんと残されています。その復刻になります。中村さん、ありがとうございます。
交流会ですが、今回は、いつものメンバーに加え、濱口元総長やIBMの橋本元社長・会長らも参加くださり、賑やかな会となりました。交流会は、2年前から恒例となった名古屋大学交響楽団OG/OBの弦楽四重奏団、山の上クァルテットによるハイドンの弦楽四重奏曲「ひばり」からスタートです。春を告げる美しい音色のアンサンブル、楽しませていただきました。
交流会の締めは、こちらも恒例、第八高等学校寮歌「伊吹おろし」と名大の学生歌「若き我等」をみんなで歌って解散です。帰りの新幹線も15分ほど遅れましたが、無事に帰ってこられました。
関東支部の幹部の皆様、素敵な会をありがとうございます。また来年もどうかよろしくお願いします。
2月7日
本日は土曜日ですが、名古屋大学の最高の賞である石井健一郎賞の授賞式がありました。第4回目となります。
今回の受賞者ですが、本学の未来社会創造機構量子科学イノベーション研究所の馬場嘉信特任教授です。馬場先生は、ナノデバイスによって工学と医療をつなぐ研究で国際的な業績を挙げられてこられた方です。例えば、マイシグナルという尿によるがん検診を行っているクライフというスタートアップは、馬場先生の技術をもとに研究室の学生(後に教員)だった安井隆雄さんがマイクロRNAを回収する手法を開発、起業に至ったという経緯があります。
奥様もご出席いただいたNIC館での授賞式の後には、場所をES館に移して、受賞記念講演会「ナノバイオデバイスと量子生命化学が拓く未来医療」がありました。こちら、馬場先生の研究をとてもわかりやすく説明していただき、本当に興味の尽きないあっという間の1時間でした。研究内容もですが、人材の育成という点でも本当に多くの研究者を育てられたとのこと、感服いたしました。学生の教育はもとより、1000本を超える論文、国際会議の講演やマスコミの登場なども多く、本当に忙しい教授時代だったことが伺えました。
終了後は学生からの質問もたくさんありました。私からも、産学連携、社会実装よりの研究を志すようになったきっかけは、という質問をさせていただいたのですが、徳島大学の薬学部に行ったことが契機とのことでした。
馬場先生のお話、今回は産学連携、社会実装に重きを置いていましたが、実は基礎寄りの研究もたくさんされていらっしゃるとのこと。馬場先生の研究の幅の広さと深さには本当に脱帽です。
馬場先生、石井健一郎賞のご受賞、おめでとうございます!


2月6日
本日の中日新聞朝刊に嬉しいニュースが載っていました。トランフォーマティブ生命分子研究所ITbMの吉村崇拠点長が内藤記念科学振興賞を受賞することが決まったとのことです。
内藤記念科学振興賞は、エーザイ株式会社の創業者の内藤豊次氏が人類の健康の増進に寄与する自然科学の基礎的研究を対象として設立したもので、1969年度から始まっていて、第一回目のその年には、本学の岡崎令治先生が受賞されてらっしゃいます。今回が第57回となり、生命系の基礎研究分野では非常に栄誉とされる賞です。理学研究科長を務められた近藤孝男先生の名前も受賞者にあります。
今回吉村さんは「脊椎動物の季節適応機構の解明とその制御」というテーマで受賞されました。動物が季節を感じる仕組みに関する研究業績になります。おめでとうございます!
午後には吉村さんに並ぶような、本学が誇る研究者たちの成果報告会がありました。次のITbMのような世界トップレベル研究拠点を目指す最先端国際研究ユニット、そして若手が分野を超えて融合研究を進める若手新分野創成研究ユニットの代表らによる報告です。一部しか聞けませんでしたが、非常に高いレベルで活発に研究を進めている、まさに本学を代表する研究者の皆さんの報告、大変楽しく拝聴させていただきました。
皆さんとびきり優秀な若手、中堅研究者なだけあって、かなりのユニット参加者が代表者も含めて、他の大学に転出、つまり引き抜かれてしまっていたことは残念でした。本学としては素晴らしい研究成果を名古屋大学で残して下さることが一番大事だと思っています。もちろん残ってさらに研究を進め、また後進の育成をしていただけることがベストです。でもちょっと悔しいですが、転出された先生方には、本学での成果をもとに、新しい場所でも引き続き活躍いただければ幸いです。
2月5日
本日は夕方から、東急ホテルでキャンパスベンチャーグランプリ中部の表彰式がありました。
第23回を迎える本ビジネスプランコンテスト、昨年は名古屋大学のチームが大賞を受賞、全国大会に進み、そこでも文部科学大臣賞を取りました。
今回も本学の学生たちですが、名古屋産業人グラブ会長賞1チーム、奨励賞2チームと健闘してくれました。この3チームとも工学研究科の大学院生たちだったのですが、後で事情を聞いたところ皆さん天野先生がリーダーをされている卓越大学院DIIの履修生でした。しかも昨年9月のシンガポール研修に参加していて、私ともその際に会っている学生が大半でした。
名古屋産業人グラブ会長賞は、光触媒を使った太陽光由来の燃料を作る、という提案、本学のシーズ技術を社会実装する試みになります。奨励賞は、ヨットの操船をAIを使って学ぶというものと、アクアリウムの水質浄化を光触媒を用いて行うというものでした。3チームとも是非この受賞を励みに、起業まで持って行って欲しいと思います。
今回は、116件という多数の応募の中から10チームが受賞されました。そのうち本学は上記DIIの3チームとアナウンスされていたのですが、じつは中部経済産業局長賞を受賞した中京大のチーム、本学の起業部で中京大の学生と本学の医学研究科の院生が出会って考えたテーマとのこと、すでに院生さんは就職していたので大学名が出なかったそうです。起業部、頑張ってますね。内容は、米糠を使ったスナックでダイエット、というプランでした。
受賞されたDIIの学生さんと、起業部のお二人とそれぞれ一緒に撮った写真をアップしておきます。おめでとうございました!
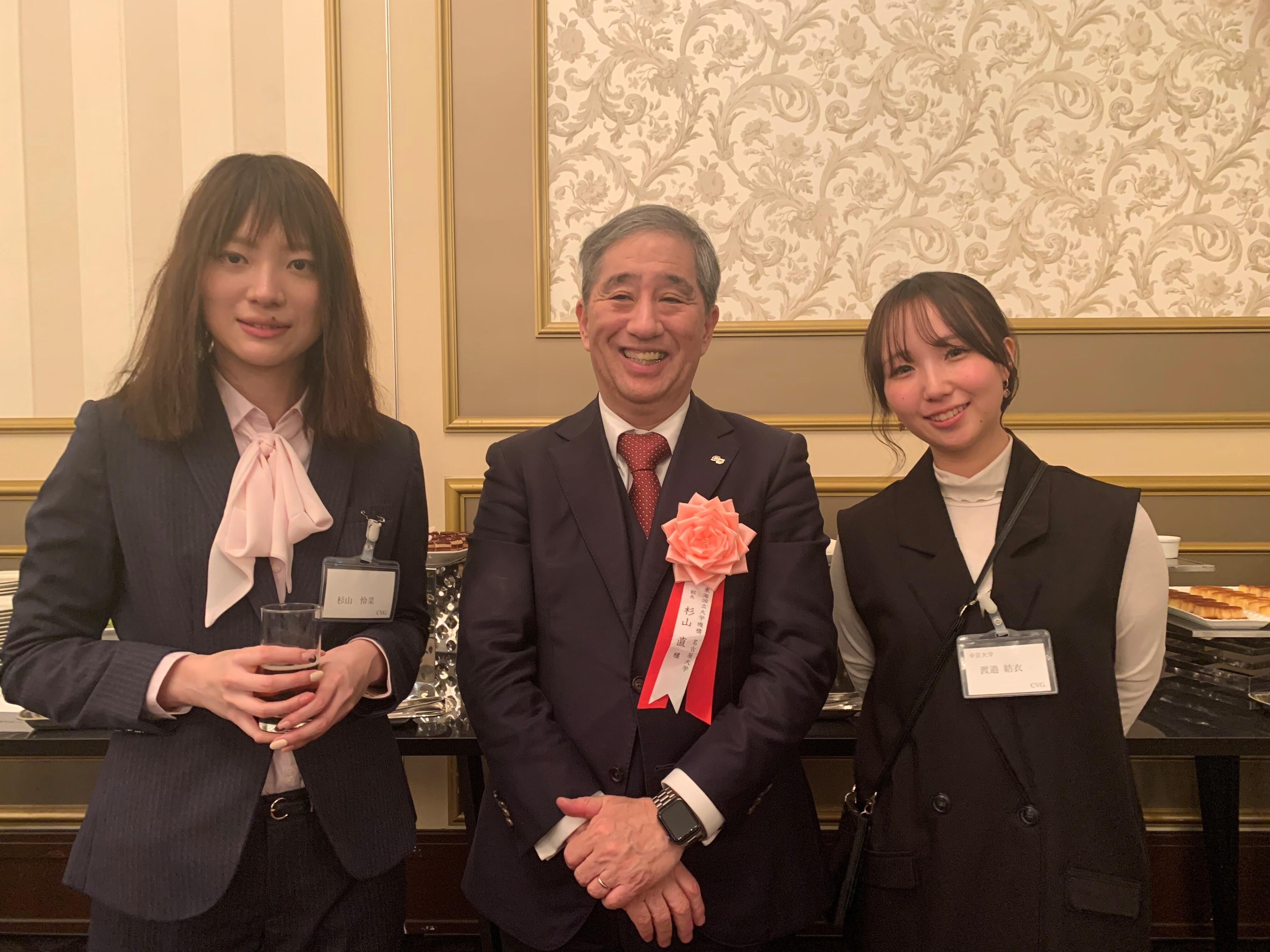

2月2日③
石田賞授賞式のあとはすぐに豊田講堂へ移動、バングラデシュのムハンマド・ダウド・アリ大使らの表敬訪問を受けました。
本学には、現在バングラデシュからの留学生が15名在籍しています。そのうち5名が学部学生です。
大使は、是非とも学部の留学生の人数を増やしたいとのご希望を述べられていました。バングラデシュで留学の説明会をやると1000人以上の学生が集まり、日本語学校もたくさんあるとのこと、日本で学びたい、働きたいという需要は相当あるようです。若年人口がとても多い国だそうですので、日本にとっても今後期待ができます。
大使には本学のG30をご紹介差し上げました。少しでもバングラデシュからの学生、増えると嬉しいですね。
ところで今回一番びっくりしたのは、名古屋市内にいる南アジア系の人口です。バングラデシュが833人、インド862人、パキスタン1,239人まではあまり変わらないのですが、なんとネパール人が15,046人もいます。これは中国人の26,038人に次ぐ二番目です。日本全体ではネパール人が23万人もいるとのこと、インド料理店の多くがネパール人経営というのも頷けます。ネパール人が経営するカレー屋は「インネパ」と呼ばれるのですね。知りませんでした。
大使の表敬訪問の後は、NIC館にとって返して、TMIのPO訪問のまとめに立ち会いました。POのお二人からは、プログラムに参加している学生との面談なども行っていただき、まとめでは、秋から予定されている最終審査に向けて有益なアドバイスをいただきました。これらアドバイスをもとに、河口コーディネーターのリーダーシップのもと、最終審査を迎えたいと思います。
それにしても行ったり来たりで、なんだか疲れた一日でした。
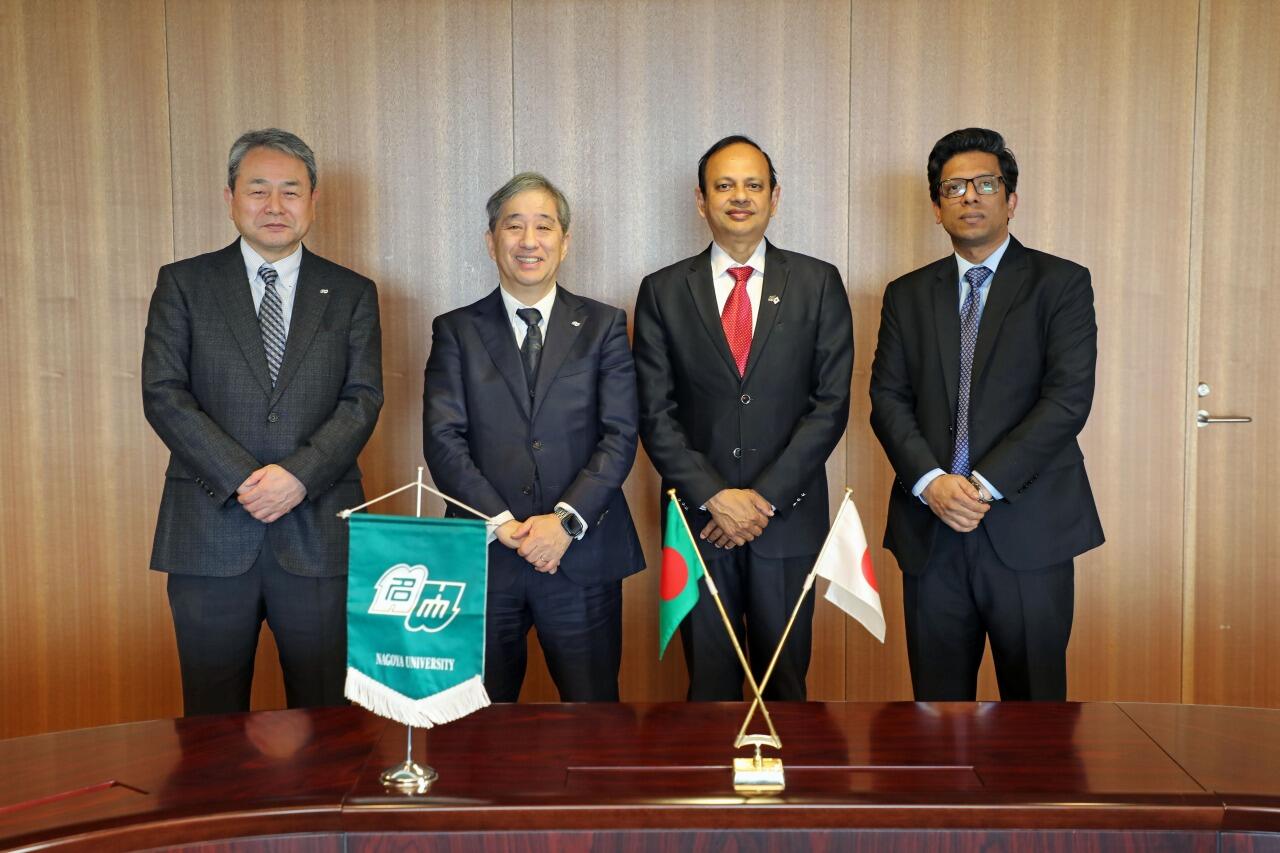
2月2日②
NIC館でのTMIのPO訪問を途中で抜けて、本部に帰ってきて名古屋大学石田賞の授賞式です。石田財団からのご寄附の意志に基づき、人文・社会科学及び自然科学の分野で、将来の発展が期待できる優れた研究能力を有する若手研究者を顕彰し、その研究意欲を高め、研究の発展を支援することを目的とし、平成24年度から顕彰制度として創設された本賞ですが、今回が14回目となります。
今回の受賞者は、情報学研究科の孟 憲巍准教授と理学研究科の田中良弥講師です。孟さんは、人の社会性を支える認知能力・モチベーションに注目、他者と共有する心、他者を記憶する心、関係性を認識する心という3つの観点から人の社会性の発達の起源について赤ちゃんを対象に包括的に研究されてこられた業績での受賞です。田中さんは、ショウジョウバエの仲間の求愛行動で羽音による歌と食料をプレゼントするという二つの異なった行動が、同じ神経回路で担われていることを分子遺伝学的手法で明らかにした業績での受賞になります。
今回は期せずしてどちらも脳・神経の関係の受賞になりました。お二人のこれからの益々の研究の発展に大いに期待しています。おめでとうございました!
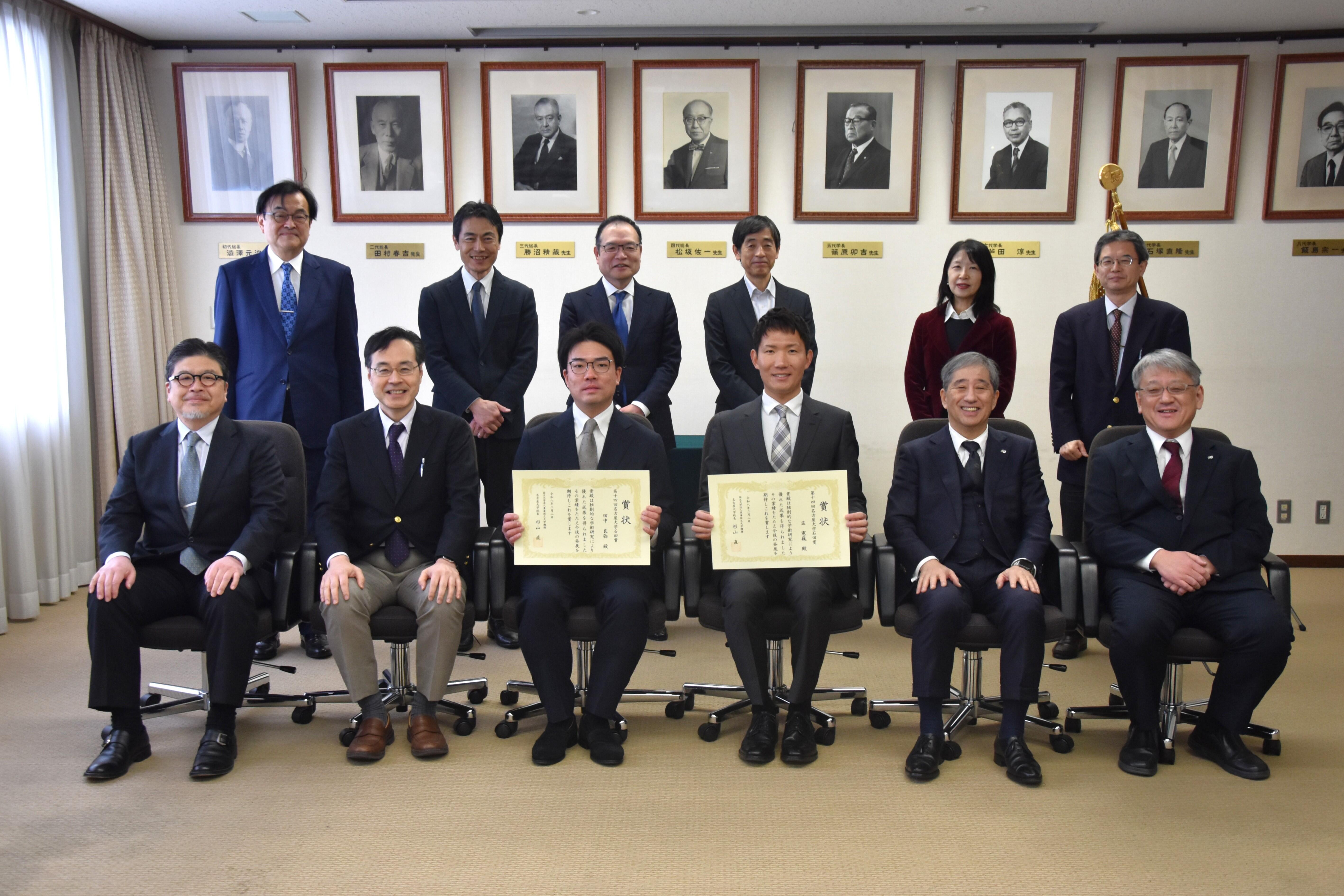

2月2日①
本日はイベントがたくさんあって目が回りました。
午前中は定例の運営会議です。私の部屋に副総長らが15名ほど集まって対面で行っています。
午後には卓越大学院TMI「ライフスタイル革命のための超学際移動イノベーション人材養成学位プログラム」のプログラム・オフィサー(PO)による現地訪問がありました。今回はこれまで6年間ずっとお付き合いいただいた海洋研究開発機構理事長の大和裕幸先生が今年度末で退任され、新たに東北大学の中沢正隆先生にPOをお願いすることになったという事情から、お二人にお越しいただきました。大和先生、これまで本当にどうもありがとうございました。また中沢先生、これからどうかよろしくお願いします。なお、中沢先生は、本学の卓越大学院DIIのPOを務めていただいたのに引き続いて本学の卓越大学院を支援いただくことになりました。ありがとうございます。
